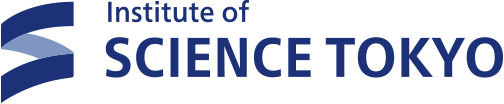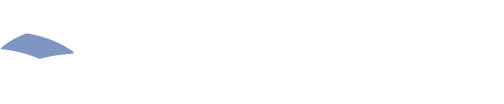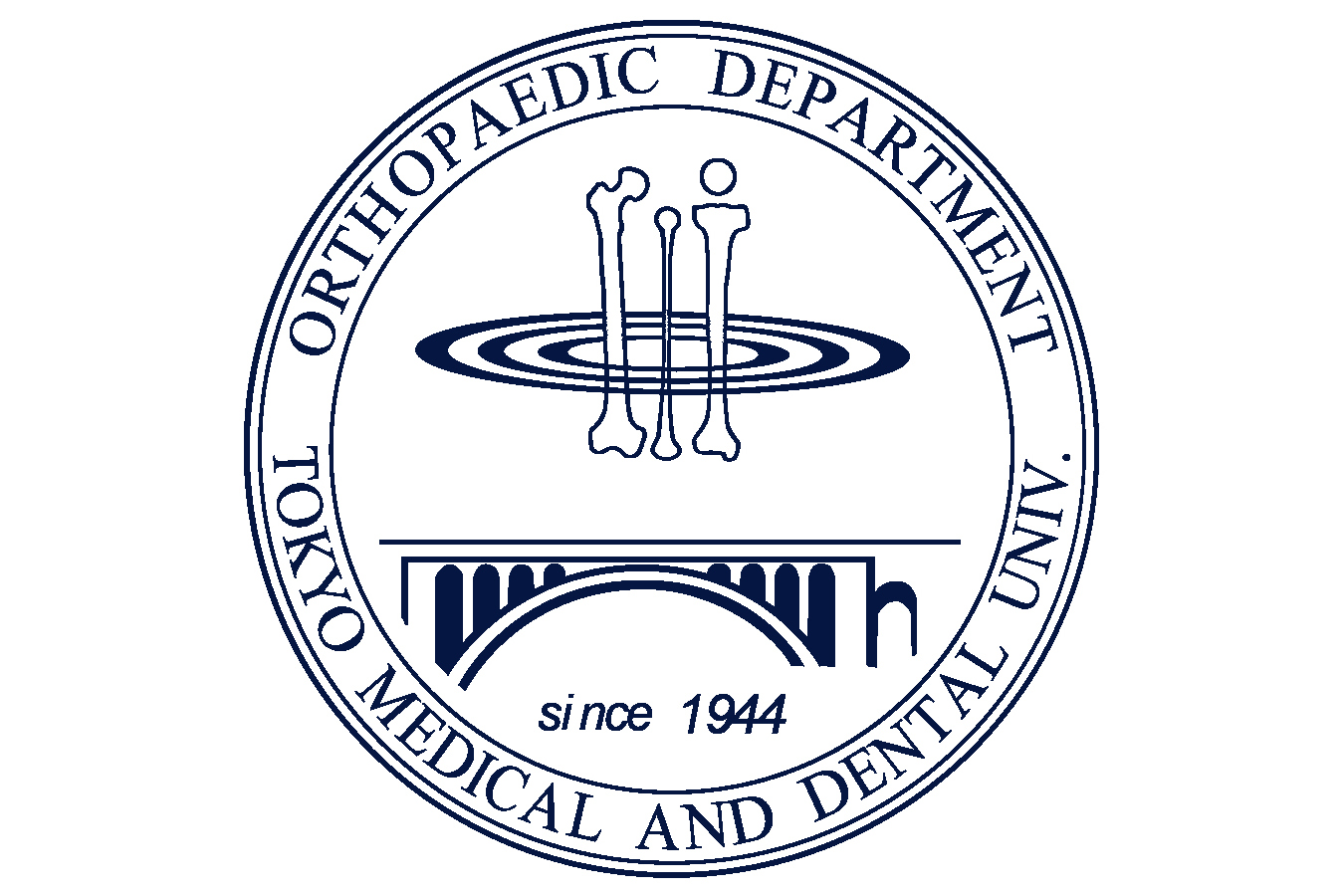
診療・研究活動の概要と目標
診療や臨床研究は主に専門診療班単位(腫瘍、脊椎、股関節、上肢、膝足、リハビリテーション)で、協力関連施設と連携して最先端の医療や研究を行っています。基礎的研究は専門班の枠には収まりきらないため、大学の基礎講座のみならず当大学附属の難治疾患研究所や生体材料工学研究所の講座と共同で研究を行っている分野も多くあります。
当教室における研究の目標は、日常臨床で生じた疑問点や治療上の問題点を臨床的ないしは基礎的手法を用いて解決することを主眼においており、いわゆる研究のための研究は極めて少ないのを特徴としております。すなわち、基礎的研究においても常に臨床の場へのフィードバックができることが求められています。
教室のあゆみ
1944~1976 青池 勇雄教授
1944年東京高等歯科医学校が東京医学歯学専門学校に改称され、全診療科を揃えた医科を作るにあたって整形外科が設立されました。その後1946年東京医科歯科大学医学部整形外科となりました。初代青池教授は、脊椎疾患、骨軟部腫瘍を中心に臨床活動を創始・発展させました。
1977~1996 古屋 光太郎教授
第2代古屋教授は、股関節、骨軟部腫瘍を中心に臨床活動を拡大し、治癒的広範切除、患肢温存手術などで骨軟部腫瘍の治療成績を世界のトップレベルにまで高めました。変形性股関節症についてはCharnley式人工股関節置換術で本邦トップレベルの成績をおさめました。脊椎、腫瘍、股関節、上肢、リハビリテーションの各専門班による診療・研究が推進され、1980年頃より新たに膝足班が設立されました。
1996~2010 四宮 謙一教授
第3代四宮教授は、脊椎脊髄外科を中心に臨床活動を拡大しました。脊髄誘発電位を用いた脊髄機能診断を確立し、頚髄症、脊髄腫瘍、側弯症などで安全な手術を実現しています。またエビデンスのある治療の確立のため、頚椎手術(前方法と後方法)や腰椎変性すべり症手術(固定の有無)に関して、前向き臨床研究を進めています。人工骨の開発や磁界測定による脊髄機能診断など臨床応用に向けた基礎的研究も手がけています。
2000年には大学院大学化に伴い、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科脊椎脊髄神経外科学分野となり、さらに新設された運動機能再建外科学分野に宗田大教授が就任しました。宗田教授は膝関節外科・スポーツ整形外科を中心に臨床活動を拡大し、世界的に注目を浴びている二重束前十字靭帯再建術を開発、優秀な治療成績をおさめています。さらに研究分野としては滑膜幹細胞を中心に用いた関節機能の再建に業績を上げています。その後2004年にそれぞれ整形外科学分野、運動器外科学分野と改称しています。
2011~2022 大川 淳教授
第4代大川教授は脊椎脊髄外科を中心としつつ医療安全向上に注力しました。まず「脊柱靭帯骨化症に関する調査研究」の全国大規模多施設疫学調査の研究代表として、世界に先駆けて手術レジストリ・全脊柱CTデータレジストリを構築し、数多くのエビデンスを創生しました。他にも先代四宮教授が始めた頚椎後縦靭帯骨化症・頚椎症性脊髄症の前向き比較研究において、頚椎前方除圧固定術のアドバンテージをまとめました。また骨粗鬆症性椎体骨折の初期装具治療について世界に規模がない300例以上の大規模多施設ランダム化比較研究を執り行い、新たなエビデンスを導出しました。基礎研究では臨床診断に応用可能なヒト脊髄の活動に伴う微弱磁界の計測を世界に先駆けて発表し、神経伝導の異常をとらえることができる世界で唯一の磁界計測診断機器を株式会社リコーと共同開発しました。
運動機能再建外科学分野では2020年に古賀英之教授が就任されました。古賀教授は膝関節外科・スポーツ整形外科を中心に臨床活動を拡大し、中程度の変性症例に対して世界で初めて半月板内方化術を考案/実行し病態に応じた骨切り術と併用し良好な成績を収めています。
応用再生医学では2014年に再生医療センターに関矢一郎教授が就任され、滑膜を利用した間葉系幹細胞移植を臨床応用に発展させました。2022年には統合教育機構 教養教育部門に2020東京オリンピックで選手村診療所長を務めた柳下和慶教授が就任され、大学では制度上不要となった体育実技による健康概念の教育を担っており、学生教育にも注力しました。
2023~ 吉井 俊貴教授
組織図
| [統合教育機構 教養教育部門]
柳下 和慶
[リハビリテーション医学分野]
[がん先端治療部] 佐藤 信吾 |
[整形外科学] 吉井 俊貴
[整形外傷外科治療開発学講座] |
[運動器外科学分野] 古賀 英之
[軟骨再生学講座] 中川 裕介 |
[再生医療研究センター] 関矢 一郎
[先端技術医療応用学講座]
[運動器機能形態学講座]
[統合イノベーション機構 オープンイノベーションセンター 医療デザイン部門] 藤田 浩二 |