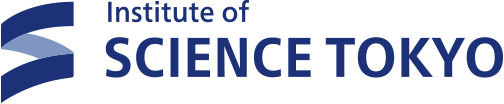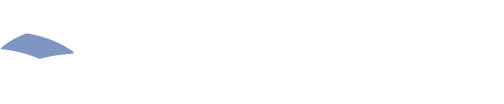第58回 日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会参加報告
大学 斎藤郁斗
今回ご縁を頂き、2025年7月17,18日に奈良県コンベンションセンターで開催されました第58回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会に参加しましたので、報告いたします。
本学会のテーマは、「啐啄同時 次世代につなぐサイエンス・パッション・アート」でした。啐啄同時(そったくどうじ)とは、鳥の雛が卵を内側から殻をつつく音(啐)と親鳥が卵の外側から殻をつつく音(啄)が同時でないと卵が孵らない様子から生まれた言葉、だそうです。これを禅宗では、師匠と弟子の呼吸が一致した時はじめて大きな悟りが開く好機となる、という意で用いるようです。
さて、全日程を通して当教室からは計22演題(うちシンポジウム5演題、パネルディスカッション1演題)の発表がありました。私は会期中、同門の先生が演者や座長をされるものは聞く前提で、プラス自分の興味あるプログラムにも積極的に参加することとしました。結果、丸二日であらゆる会場を飛び回る非常に濃密な時間となり、当教室の本領域における活躍が骨身に染みて実感(痛感?)できました。
その中で今回まず特筆すべきこととしては、本領域における本学脊椎グループの認知度と活躍、であったように感じました。平井准教授が「転移性脊椎腫瘍に対する当院の取り組み」でシンポジストを務められたほか、上杉先生と山田賢先生が一般口演で2題のご発表をされました。本学の班をこえた緊密かつ円滑な診療連携が高く評価されている証であり、本学の存在感をさらに高めたものと思いました。

また、がん研有明病院の松本先生、阿江先生をはじめ多くの先生が講演、パネルディスカッションの座長を務められており、当グループ全体で学会を盛り上げていく雰囲気が強く感じられました。特別講演・シンポジウムではデジタルトランスフォーメーション、AIを用いたがん診療の取り組みについてもフィーチャーされており、当教室の先生方がその中でも先んじた取り組みを発表されていた点が特に印象的でした。

本学会では個人的に2点、特に興味深いと感じる出来事がありました。まず近年話題の『医療とAI』に関する講演内の出来事です。ある演者が、「若手が論文の抄読や作成時にAIを使うのを認めるか?」という問題提起に対し、「AIに任せきりでは批判的吟味能力(critical thinking)がつかないという理由から推奨しない」、という答えを提示する場面がありました。これには私も、直前の大学抄読会でその重要性を学んだばかりでしたので、大いに納得したものでした。しかしこの直後、大変若い先生がすっくと質問に立ち、「雑用に追われやむを得ず抄読会などにAIを使用している。本当はAIに書類やサマリーなどの雑用をやらせ、私が論文を読みたいのだが、あべこべになっている。どうしたら良いか?」と問うものでした。医療現場ではAI技術をどのように実装していくべきなのか、過渡期の問題点をあぶりだす重要な問いかけだと感じました。
またAYA世代肉腫患者のアンメットニーズに関するパネルディスカッションですが、こちらには埼玉がんセンターの五木田先生も登壇されました。このセッションでトリを務めたAYA世代がんサバイバー患者さん2名の講演が、特に胸を打つものでした。私とそう歳の離れていないお二人でしたが、言葉の重さや立ち振る舞いの成熟した様子を見て、若くから病気と向き合い続けた方々の強さを痛感しました。AYA世代患者さんたちがよりよく生きていくために医療側ができることはなにか、時間や場所づくりはできないか、など思いを致すヒントがたくさん聞けた、貴重な体験であったと思います。

本会は同門の先生が多数活躍された、学びと実りの多い学会でした。また、グループ内にとどまらず、班や科や施設すら超えた連携と結束力が感じられた時間でもありました。今回の学びを生かし、若輩者ながら精進して参りますので、今後ともご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。